京都を訪れると鴨川のほとりでゆったりとした時間を過ごす方が多くいますよね。特に三条大橋のあたりは夏には川の上に床が出て賑わい、川べりには等間隔に座るカップルの姿も見られます。
穏やかで風光明媚な鴨川ですが、実は千年以上にわたって恐ろしい歴史の舞台でした。
鴨川の河原、特に三条河原と六条河原はかつて多くの罪人が処刑され生首がさらされた場所だったのです。
歴史の教科書やドラマで、これらの河原の名前を聞いたことがあるかもしれません。
「三条河原と六条河原の違いって何だろう?」
と思ったことはありませんか?
この記事では三条河原と六条河原の地理的な違いやそれぞれの場所で起きた歴史的な出来事。両者の役割の違いについて分かりやすく解説します。
恐ろしい過去を持つ河原が、今どのように姿を変えたのかにも触れていきます。
三条河原と六条河原はどこにある?現在の様子
三条河原の現在
まず、三条河原と六条河原が現在の京都のどこにあたるのかを見てみましょう。
三条河原は現在の三条大橋の周辺、鴨川の河川敷を指します。
ここは京都の中心部にあたり今では多くの観光客や地元の人々で賑わう場所です。橋のたもとにはおしゃれなカフェやレストランが立ち並び川沿いは遊歩道として整備されています。先ほどもお話ししたように夏には鴨川納涼床が出て涼やかな風を感じながら食事が楽しめます。

現在の三条河原
六条河原の現在
一方、六条河原の処刑場跡は現在の五条大橋から正面橋にかけての鴨川沿いにあたります。
三条河原よりも少し下流に位置する場所です。このあたりは三条周辺ほどの賑やかさはありませんが、整備された公園や遊歩道があり地元の住民が散策したり休憩したりする姿が見られます。
鴨川は南北に流れていますから、大まかに言うと上流側にあるのが三条河原、下流側にあるのが六条河原ということになりますね。
なぜ河原が処刑場になったのか?
なぜ河原が選ばれたのか
なぜ、鴨川の河原が処刑場として使われることが多かったのでしょうか。いくつか理由が考えられています。
一つは、人目につきやすい場所だったということです。都の中心を流れる鴨川の河原は、多くの人が行き交う場所でした。ここで処刑やさらし首を行うことで、見せしめとしての効果が高かったと考えられます。
また、ケガレを清める場所だったから?
処刑は血が流れる行為であり、当時の人々にとってはケガレと結びつくものでした。清らかな水が流れる河原でこれを行うことで、ケガレを洗い流すという意味合いを持たせた、という説もあります。
処刑場としての歴史はいつから?
鴨川の河原が処刑場として使われるようになったのは古く平安時代にさかのぼります。特に六条河原は、平安時代後期から処刑場としての記録が多く残っています。三条河原も後に処刑やさらし首の場所として重要になっていきます。
千年以上にわたって、鴨川の河原は静かに歴史の血なまぐさい側面を見つめてきたのです。
歴史を刻んだ三条河原での出来事
豊臣秀次とその妻子たちの悲劇
三条河原は処刑そのものよりも、処刑された人物の首がさらされる場所として知られることが多いようです。都の中心部に近く多くの人が通行するため見せしめには効果的な場所でした。
中でも歴史に深く刻まれているのが豊臣秀次の妻子たちの悲劇です。天下人・豊臣秀吉の後継者だった秀次が謀反の疑いをかけられて自害した後、慶長2年(1595年)その妻子や側近など39人が三条河原に引き出されました。
幼い子どもたちを含め女たちが次々と秀次の生首が置かれた塚の前で処刑されていったのです。その凄惨な光景は見物していた人々が思わず目を背け、「あまりにも酷い」と役人に罵声を浴びせたほどでした。遺体は大きな穴にまとめて埋められ、その上に秀次の首を納めた塚が作られました。
この塚は「畜生塚」などと呼ばれましたが、後に豊臣秀次らを供養するために瑞泉寺が建てられました。瑞泉寺には今も秀次とその妻子たち、そして殉死した家臣たちの供養塔が静かに立っています。

瑞泉寺の豊臣秀次と家族の供養塔
三条河原にゆかりのある人物たち
この三条河原で処刑やさらし首になったことが伝わる主な人物には以下のような人々がいます。
| 時代 | 人物 | 出来事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 安土桃山時代 | |||
| 豊臣秀次 | (秀吉の後継者問題) | さらし首 | |
| 豊臣秀次の妻子39人 | (秀吉の後継者問題) | 処刑 | |
| 石川五右衛門と家族 | (盗賊) | 油で釜ゆで | |
| 石田三成 小西行長 恵瓊 |
関ヶ原合戦 | さらし首 (六条河原で斬首後) |
|
| 江戸時代幕末 | |||
| 島田左近 | 攘夷運動 | さらし首 | |
| 本間精一郎 | 攘夷運動 | さらし首 | |
| 公家・幕府要人多数 | 攘夷運動 | さらし首 | |
| 近藤勇 | 戊辰戦争 | さらし首 (他所で斬首後) |
|
他にも関ヶ原の戦いに敗れた石田三成や、新選組局長の近藤勇も別の場所で命を落とした後、その首が三条河原に運ばれてさらされています。
多くの命が散った六条河原での出来事
平安時代からの処刑の記録
六条河原は三条河原よりも古くから処刑が行われる場所として使われることが多かったようです。
都の中心部(内裏)から少し離れている方が処刑という行為を行う場所として適していたのかもしれません。
平安時代末期、保元・平治の乱の後、六条河原で多くの武士が処刑されました。特に平治の乱で敗れた藤原信頼が斬首されたのは鴨川の河原で処刑された有名人としては初期の例と言えるでしょう。
源平合戦で敗れた平家の武将たちも、この六条河原で最期を迎えた者が少なくありませんでした。
室町時代の大きな出来事
室町時代には、罪人や合戦で敗れた武将などが六条河原で処刑されています。嘉吉の乱で敗れた赤松満祐の一族の首がさらされたのも六条河原でした。また、禁闕の変で反乱を起こした日野資親ら50人がここで一度に処刑された記録も残っています。
六条河原にゆかりのある人物たち
この六条河原(七条河原も含む)で、処刑やさらし首になったことが伝わる主な人物には、以下のような人々がいます。
| 時代 | 人物 | 出来事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 平安時代 | |||
| 平将門 | 平将門の乱 | さらし首 (七条河原) |
|
| 藤原信頼 | 平治の乱 | 斬首 | |
| 源義平 | 平治の乱 | 斬首 | |
| 平宗盛 平清宗 |
源平合戦 | さらし首 | |
| 平能宗 藤原忠清 |
源平合戦 | 斬首 | |
| 鎌倉時代 | |||
| 安楽房承元 | 法難 | 斬首 | |
| 室町時代 | |||
| 春日顕国 | 南北朝 | さらし首 | |
| 赤松満祐 赤松義雄 真操 |
嘉吉の乱 | さらし首 | |
| 日野資親ら50人 | 禁闕の変 | 斬首 | |
| 安土桃山時代 | |||
| 石田三成 小西行長 恵瓊 |
関ヶ原合戦 | 斬首 (三条河原でさらし首) |
|
| 江戸時代前期 | |||
| 長宗我部盛親 | 大坂夏の陣 | 斬首 | |
| 豊臣国松 | 大坂夏の陣 | 斬首 | |
| キリシタン多数 | キリシタン弾圧 | 斬首 | |
これが重要!三条河原と六条河原の決定的な違い
地理的な場所の違い
ここまで三条河原と六条河原の歴史を見てきました。結局のところ、この二つにはどのような違いがあるのでしょうか?
最も分かりやすい違いはやはり地理的な位置です。三条河原が上流側(三条大橋周辺)、六条河原が下流側(五条大橋~正面橋あたり)にあるという点です。
歴史的な役割の違い
歴史的な使われ方は厳密なルールがあるわけではありませんが、傾向としては違いが見られます。
- 六条河原: 処刑そのものが行われる場所として使われることが比較的多かったようです。できるだけ都の中心部から離れている方が、処刑という行為を行う場所としてふさわしいとされていたのかもしれません。
- 三条河原: 処刑された人物の首をさらす場所として使われることが多かったようです。多くの人が行き交う都の中心部に近いため、見せしめとしての効果を狙ったと考えられます。
もちろん、時代や事件によっては三条河原で処刑が行われたり、六条河原でさらし首が行われたこともあります。完全に役割が分かれていたわけではありません。でも、処刑なら六条河原、さらし首なら三条河原が行われる傾向があったと覚えておくと、わかりやすいですね。
過去と現在をつなぐ三条河原と六条河原
血に染まった過去と現在の姿
凄惨な歴史の舞台となった三条河原と六条河原ですが、今ではその面影はほとんどありません。
三条河原は先に書いた通り京都を代表する観光地の一つとして賑わっています。かつて多くの血が流れた場所で、人々が楽しそうに過ごしている光景を見ると随分と時代が違うのだなと思います。
六条河原周辺も静かな憩いの場などになっていて、かつての処刑場の雰囲気は感じられません。
歴史を伝える供養の場所
でも悲惨な歴史が忘れられたわけではありません。豊臣秀次らを供養する瑞泉寺のように、ひっそりとその歴史を今に伝える場所もあります。
歴史を知った上でこれらの場所を訪れると、普段見ている風景が全く違って見えてくるものです。賑わいの中に隠された過去や静かな場所が秘める悲しい歴史。京都の街の奥深さを感じられるかもしれません。
まとめ
この記事では京都の鴨川沿いにある歴史的な場所、三条河原と六条河原の「違い」に焦点を当てて解説しました。
三条河原は現在の三条大橋周辺、六条河原は現在の五条大橋から正面橋あたりに位置し鴨川の上流側と下流側にあるという地理的な違いがあります。
歴史的には、どちらも処刑場やさらし首の場所として使われました。でも傾向として六条河原では処刑そのもの、三条河原では処刑された首をさらすという役割分担が見られました。豊臣秀次の妻子惨殺や石田三成、近藤勇といった歴史上の人物が、これらの河原で最期を迎えたり、その首がさらされたりしています。
かつて血に染まった河原は今では穏やかな公園や市民の憩いの場、観光地へと姿を変えました。
でも、その歴史を知って現在の風景の中に過去の出来事を重ね合わせると、京都が持つ長い歴史と奥深さを感じることができると思いますよ。

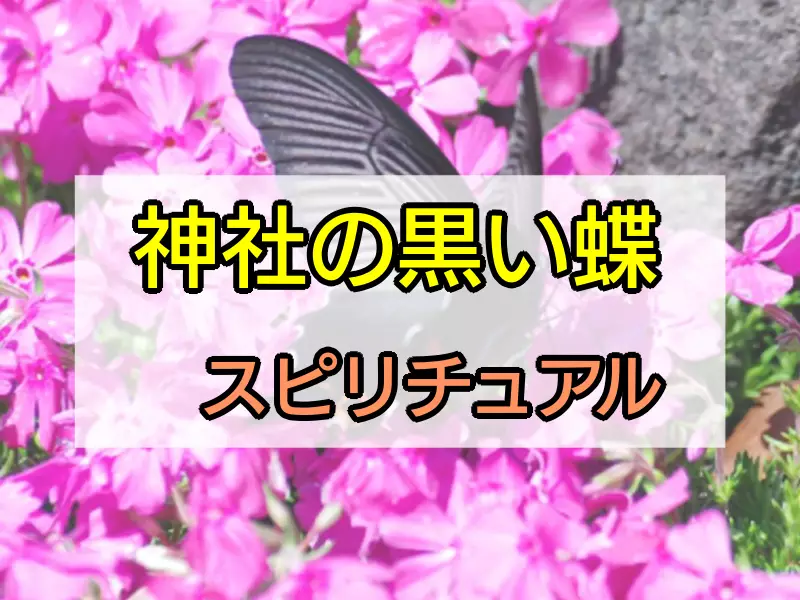




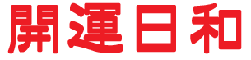
コメント