2022年(令和4年)2月3日は節分ですね。(2月2日の年もあります)
どうして節分に豆をまくのでしょうか?
そもそも節分とは何でしょうか?
鬼ってなんでしょうか?単に悪い者と思っているかもしれません。
現代では様々な意味に「鬼」という言葉が使われますから、本当の意味がわからなくなっています。
節分で追い払う鬼は「病気を運んでくる悪霊のことなのです」
今、世の中では新型コロナウイルスが流行しています。でも疫病に苦しんでいるのは古代の人も同じ。
疫病を払う行事が豆まきの起源でした。
なぜ節分に疫病を払う行事をするのか?の由来と作法を紹介します。
節分とは
節分のもともとの意味は「季節の分かれ目」です。
暦では季節の始まりを立春・立夏・立秋・立冬といいます。その前日が「節分」と決められています。
2022年は
2月4日が 立春 ですから
2月3日が 節分 なのですね。
節分の意味についてはこちらで紹介しています。

春分の前日に豆まきをする理由
春分は1年の始まり
節分は1年に4回来ます。でも豆まきをするのは春分の前日の節分だけです。
昔は1年の始まりは「春分」でした。つまり「春分が元旦」だったのです。
だから正月のことを「新春」というのですね。
年賀状に書くときに「どうして冬なのに新春なんだろう」と思ったことがあるのではないでしょうか?昔の暦で春の始まりが1年の始まりだった名残なのです。
豆まきの起源は追儺
豆まきのもとになったのは、平安時代に行われていた 追儺(ついな)の儀式です。
古代中国では1年の終わりの日(大晦日)に 儺(ダ あるいは ナ)という厄払いの行事を行っていました。
最初は疫病や災いをもたらす悪霊や死霊を追い払うための儀式でした。
儺には「はらう」という意味があります。病気や悪霊を追い払う行事です。周王朝(紀元前11~3世紀)のころから行われていたようです。
古代には年に四回行っていました。漢の時代に12月だけになり。
唐の時代に大晦日の行事になりました。
日本では飛鳥時代の慶雲3年(703年)に行われたのが最も古い記録です。その後、追儺(ついな)や「鬼やらい」という名前で呼ばれるようになり。奈良時代、平安時代と宮中行事として続きました。
「追儺」は室町時代の南北朝のころに宮中行事としては途絶えましたが。「豆まき」という形を変えて武家社会に広まり。江戸時代には庶民も行うようになりました。
鬼は目に見えない悪霊や死霊
古代中国では病気を起こす死霊や悪霊を 鬼(キ)といいました。鬼(キ)は霊なので目に見えません。
日本では「おに」と呼ばれます。鬼は見えないので 隠(おん)とよばれ「おん」が「おに」になったと考えられます。古代日本でも病気を起こす悪霊・疫病神は目に見えない存在と考えられていました。
鬼=目に見えない霊的なもの。だったのです。
鬼を払う者が鬼になってしまった
儺の行事では目に見えない鬼を方相氏(ほうそうし)が目に見えない悪霊を追い払います。方相氏は四つ目で熊の皮を被り、赤と黒の服を着て、鉾と盾を持っています。方相氏は侲子や儺と呼ばれる仲間をひきつれています。方相氏と仲間は目に見えない鬼を追いかけたり、米・豆・矢を投げて鬼を退治します
。米・豆・矢には霊力があって悪霊を払うを考えられたからです。
儺の習慣は日本に伝わりました。西暦706年。文武天皇の治世には都で疫病が流行り儺の儀式を行いました。宮中では12月の大晦日には追儺の儀式を行うようになります。
儺は「おにやらい」ともいいました。「おにやらい」とは「疫病をおこす悪霊を追い払う」という意味です。
日本に伝わった方相氏も4つ目ですが。熊の毛皮ではなく着物をきた人間の姿をしています。仏教の羅刹や夜叉の影響を受けた怖い姿で表現されることもあります。
平安時代になっても宮中で盛んに追儺が行われました。ところが目に見えない鬼を追いかける方相氏と儺の姿をみた平安の人々は方相氏が鬼だと思うようになりました。
行事の名前も 追儺(ついな)になりました。
怖い形相をした怪人?が走り回っているのです。事情をよく知らない人がみたら目に見えない鬼よりも方相氏の方がよほど怖いです。
そこで人々は「怖い姿の鬼(実は方相氏)が侲子たちに追いかけられているのだ」と考えたのです。
平安時代にはほぼ現代人が考える鬼の姿に近いものが出来上がっていました。
目に見えない悪霊(鬼)を方相氏が追う払う行事が、鬼の役目をする方相氏を人々が追い払う行事になってしまったのです。
これが現在の豆まきの起源のひとつです。
でも日本の追儺の行事では「矢」は使いますが「豆」は使いません。
桃の弓と葦の矢を使います。
桃には魔を払う力があると考えられたからです。
「桃太郎」で鬼を退治する役目が桃から生まれた人物なのも、ここからきています。
追儺の儀式は鎌倉時代になると衰退。宮中では行われなくなります。現在では一部の神社仏閣で行われています。
「追儺」や「鬼やらい」は悪霊を追い払う行事の名前として使われ続けます。
鬼やらいに豆を使う理由
鬼やらいに「豆」が登場するのは室町時代から。
豆や穀物には神の力が宿っている・魔除けの力が宿っている。とされました。また「まめ」は「魔滅」につながることから縁起がいいとされました。
豆は鬼そのものにぶつけたり、鬼の目にぶつけて追い払います。
室町時代に書かれた「壒嚢鈔(あいのしょう)」という辞典には、節分の夜に豆まきをする理由が書かれています。
宇多天皇(平安時代)のころ。鞍馬の奥にある僧正谷や美曽路池(深泥池)の穴から鬼神が出てきて都を荒らしていました。あるとき毘沙門天が現れて七人の博士を呼び、三石三斗(約600リットル)の大豆で鬼の目を打てと命じたといいます。博士たちは祈祷したのち豆を使って鬼を退治して穴を封じました。
鬼の目にぶつけるから「魔目」ともいいます。
豆まきの作法
現代に伝わる豆まきの作法を紹介します。地方によっても少しずつちがうところもあります。
豆まきは、節分の夜に行います。鬼は夜にやって来るからです。古来より夜は霊の活動する時間とされました。疫病や不幸を運んでくる悪霊も夜活動するのです。
豆まきには炒った大豆を使います。
炒った豆を使うのは、外に撒いた豆は厄がついているので食べない。捨てるものだからです。そのまま放置しておくと芽が出てしまうので、芽が出ないように炒ります。
ていねいな地方では前の日から神棚にお供えした豆を使うところもあります。
「鬼は外」と言いながら、家の中から外に向かって豆を投げます。
「福は内」と言いながら、家の外から中に向かって豆を投げます。
を撒き終わったら窓や戸を閉めて福が逃げないようにします。
家の中に撒いた豆を自分の年齢(数え年)の数だけ豆を食べます。すると健康になれるといわれます。
平和になれた現代人は「擬人化した鬼に豆をぶつけるのは可愛そう」と思うかもしれません。
厄払いが目的ですから。無理して人間が鬼の役目をする必要はありません。
イベントとして行うなら鬼役はあったほうが盛り上がりますけれど。そういう役(厄)を引き受けてくれる人がいればそれもいいと思います。
豆を投げる相手は目に見えませんから。何もない空間に豆を投げるのが本当の方法です。
それに鬼(おに)と言ってますけれど豆まきで想定される相手は童話の「泣いた赤鬼」に出てくるような心優しい鬼ではありません。
その正体は疫病や不幸を運んでくる恐ろしいものです。
あなたは病気になったら「ウイルスや病原菌が可愛そうだから治療しない、薬をのまない」と思うでしょうか?
豆をぶつける相手はキャラクターではなく「病気や不幸を運んでくる目に見えないもの」なのです。
遠慮なく豆をまいて病気や不幸を運んでくるものを追い払いましょう。
最近では家庭で炒った豆を作るのは大変なので予め炒った豆を販売しているところもあります。
お手軽にできる厄除けなので家族みんなでやってみてはいかがでしょうか?

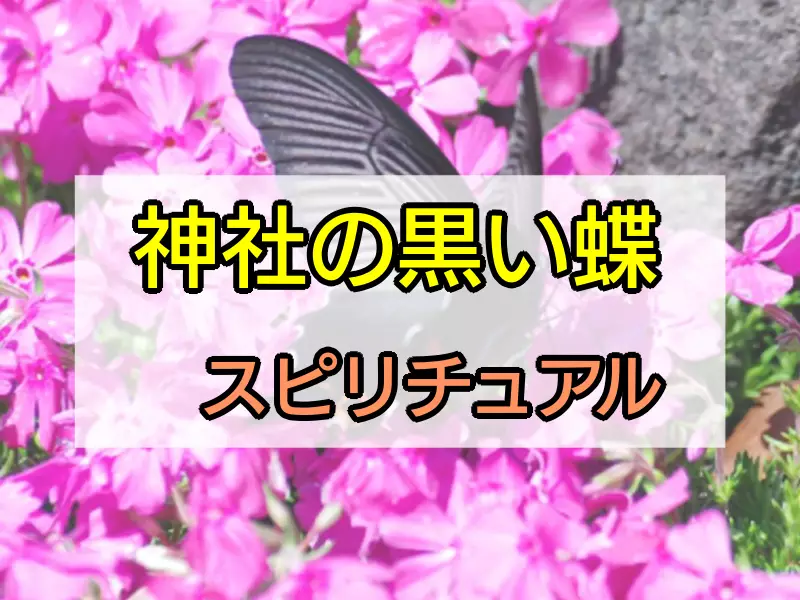




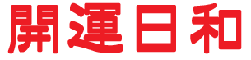

コメント